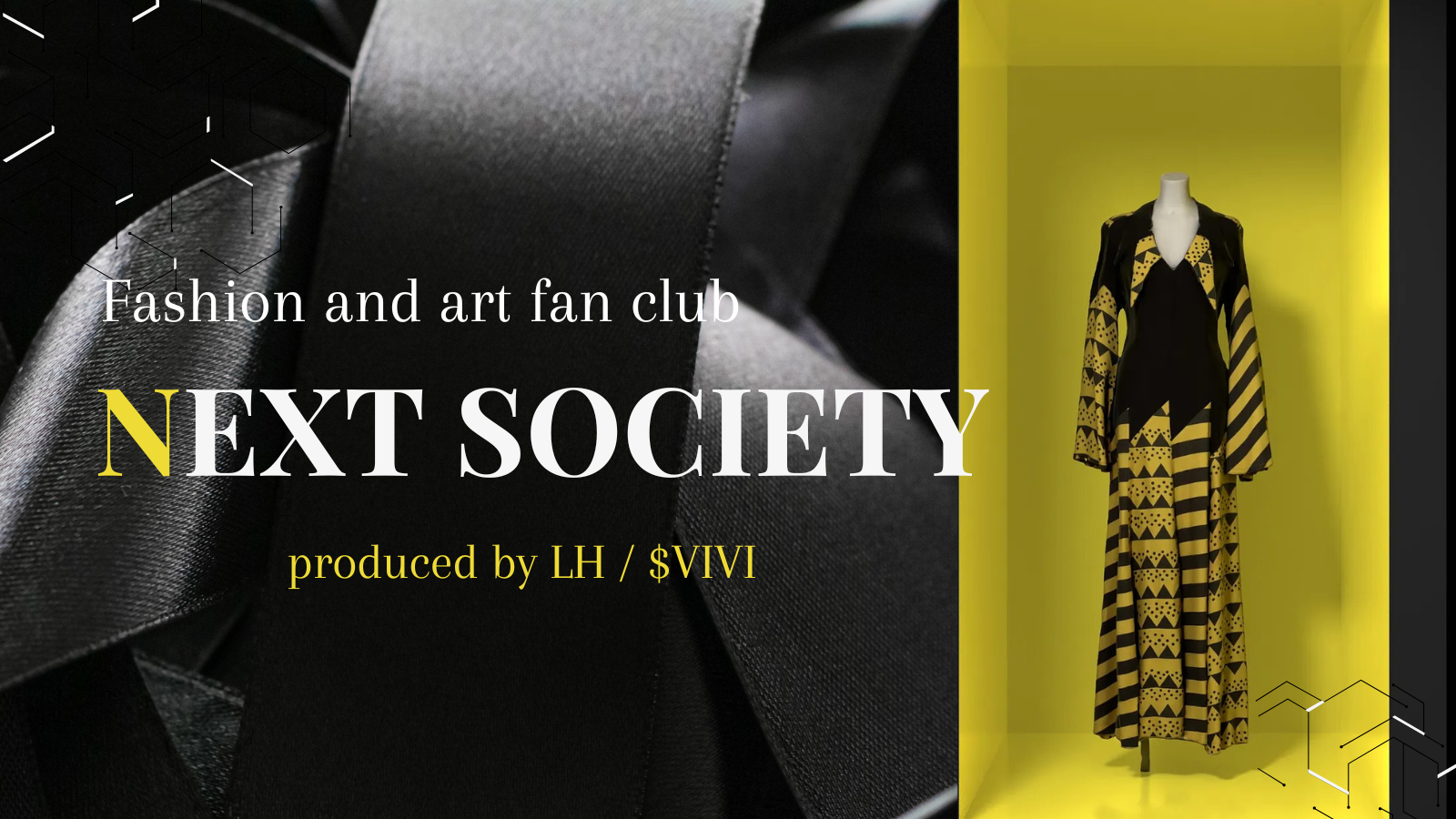Anne-Marie Beretta “Sleeveless Dress”(Spring/Summer 1984)

■知的女性のための“新しいアーマー”
1980年代、パリ。女性たちが本格的に社会進出を果たし、ジェンダー平等の流れが現実になった時代。
Anne-Marie Beretta(アンヌ=マリー・ベレッタ)は、そんな変革期の空気を着る人のために、これまでにない“新しい日常着”を提案した。
“知的な女性のアーマー”。このワードが、そのままベレッタの服を言い表している。
パワーショルダーに代表される“肩”の強調は、女性がビジネスや社会に立ち向かう意思の象徴だった。
だがベレッタは、単なる流行や男性的な模倣ではなく、“女性のための美しさと機能性”を徹底して追求したデザイナーだった。
■伝統の枠を超える、現代建築的アプローチ
ベレッタは1937年フランス生まれ。
イラストレーターを経てオートクチュールの技術を学び、Pierre Balmain、André Courrègesといった名門で経験を積んだ。
とりわけ1970年代にはクリストバル・バレンシアガのメゾンにも携わり、“構造の魔術師”として評価されていく。
「建築家か彫刻家のよう」とも称されるそのアプローチは、不要な装飾を排し、ミニマルなディテールと大胆なプロポーションを両立させるもの。
一見“日常着”に見えて、着る人の動きや気分によってシルエットが劇的に変化する。
これはベレッタが幼少期から鍛えたデッサン力、そして高度なオートクチュールの裁縫技術に裏打ちされている。
■ドレスの構造美:ディテール解剖
今回取り上げるこの1984年春夏のスリーブレスドレスは、一枚のコットンリネン地に、抽象的な白のパターンが織り込まれたもの。
紺地の上に映えるパターンは、伝統的な女性らしさとは一線を画し、現代的で知的な“強さ”を印象付けている。
特筆すべきは、ウエスト両脇に寄せられたドレープ(ひだ)。
着用者がここに手を入れて生地を持ち上げると、平行に見える布のラインが生まれ、ベレッタらしい構築的な美しさが際立つ。
また、ウエストをベルトアップすることでドレープがさらに広がり、ボリュームと立体感が強調される仕掛けもユニークだ。
前面にあしらわれた複数のスナップボタンは、彼女のレインウェアやスポーツウェアデザインの経験を活かしたディテールであり、機能性と審美性を見事に両立。
スナップボタン自体も、ファッション史的には「スポーティな意匠を女性のドレスに採用した最初期の事例」のひとつとして語り継がれることが多い。
■ベレッタの思想:「内面をデザインする」
Anne-Marie Berettaは「服をデザインするということは、女性を外側だけでなく内側からも見つめること」と語っている。
社会に出て自分らしく生きる女性たちが、気負わず、美しく、かつ自信を持てる服を。
“Easy to wear, minimal in detail, but striking in regards to proportion and cut.”―
この信念は、デザイナーとしてのキャリアを通して一貫していた。
このドレスもまた、外からの視線に媚びる装飾ではなく、着る本人が“自分の美学”を体現できる一着として生み出された。
軽やかで実用的なコットンリネン、幾何学的で知的なパターン、そして着方によって変わるボリューム設計―
「美しさは、着る人の内側から引き出される」。ベレッタの服が時代を超えて愛される理由だ。
■1980sパリモードの転換点
1980年代のパリは、ジャン=ポール・ゴルチエ、クロード・モンタナ、ティエリー・ミュグレーといった“新しい女らしさ”を定義したデザイナーたちが活躍した時代。
だが、Anne-Marie Berettaはその中でも独自の道を歩み続けた。
時代の流れに抗うことなく、むしろ流れの“先”を読む。
男性的な力の象徴を女性服に持ち込むのではなく、あくまで“女性自身の人生”に寄り添うシルエットを選ぶ。
この柔軟さと芯の強さが、ベレッタのクリエイションを唯一無二のものにしている。
■着る人の“選択”が完成させる服
このスリーブレスドレスは、着る人自身がどう着るかで表情が大きく変わる。
ウエストを絞るのか、ドレープを持ち上げて見せるのか、あるいはラフに手を入れて“動き”を楽しむのか―
“女性自身の生き方”がシルエットに現れるのだ。
服が主役ではない。
その日どんな気分で袖を通すか、どんな自分で社会に立つか―
ベレッタはそうした“内面の選択”こそが、真のモードだと信じていた。
■ファッションアナトミーのまとめ
Anne-Marie Berettaのこの一着には、
・1980年代の社会変化と女性の自立
・オートクチュールの伝統と現代的な建築美
・装飾性ではなく、構造美へのこだわり
・着る人自身が完成させる“余白”
といった、時代と哲学が凝縮されている。
ファッションアナトミーは、服の構造を解剖しながら、その向こうにある時代の思想や生き方まで掘り下げていく。
このドレスが今ここに残っているのは、単なる流行やブランドの枠を超えた“物語”が宿っているからだろう。
Powerd by FanClub3.0
©2025 NEXT SOCIETY